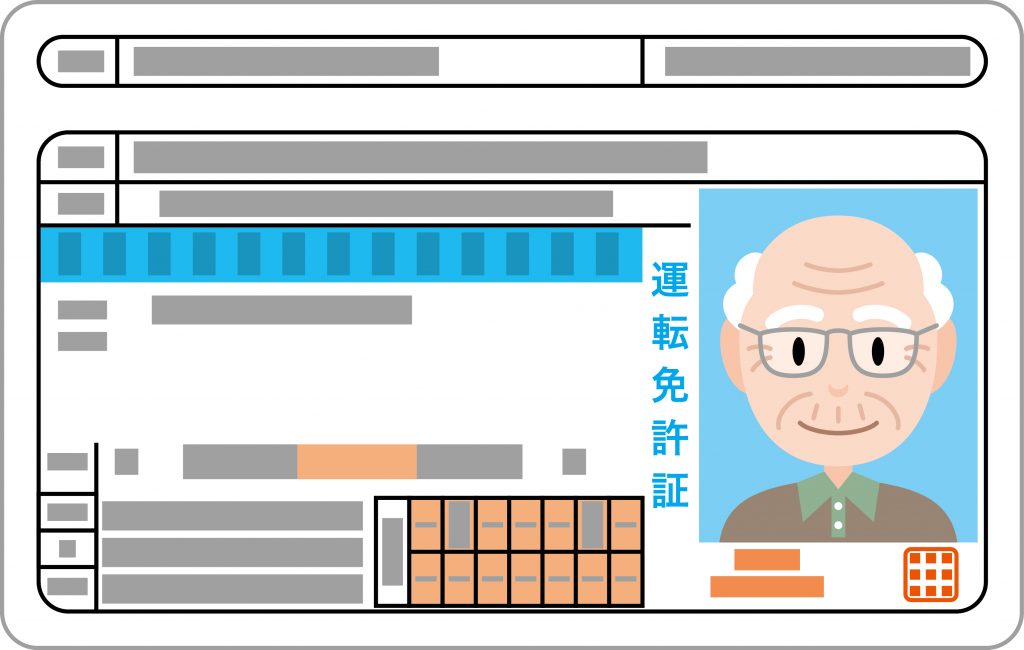高齢者の自動車事故のニュースを聞くと自分も気をつけなきゃなって思います。
特に、道路とは違って明確な運転ルールがないスーパーの駐車場などへ行くと、不注意極まりない運転の仕方をしているご老人にお目に掛かります。
何度か危ない目にも合っていますので、老人はほんとに注意力、判断力が鈍くなっているんだなって思います。
ところで、高齢者の運転免許更新って、いったい何歳まで許されているんでしょうか?
私のように地方に住んでいると、車がないと生活に支障が出ると言う方も多いのではないでしょうか?
もし車が運転できなくなったら、どうしたら良いのでしょうか?
子供と同居しているからヘルプがあると言う方もいますが、子供がいない方、私のように別居して近くにいないと言う方にとっては不安ですよね。
転ばぬ先の杖、ちょっと気になったので色々と調べてみました。
運転免許更新の年齢の上限は決められていない
そうなんです、運転免許の更新の年齢制限はないんです。
ですから一度取得してしまえば、更新手続きをすれば、ず~っと車の運転ができることになっています。
とは言え、昨今の高齢者の事故の多さから、運転免許証更新の際には以下の講習会に参加して「運転する能力あり」と認めてもらう必要があります。
■70歳から74歳までの方の免許更新:高齢者講習
「運転適性検査器材による指導」と「実車による指導」を受けることで、免許の更新になります。
■75歳以上の方の免許更新:認知機能検査と高齢者講習
認知機能の検査をして、記憶力・判断力を確かめます。仮に認知症の疑いがあれば医師の診断を受ける必要があります。それ以外の方は、70歳から74歳までの方と同じ高齢者講習を受けて免許の更新になります。
加齢から来る記憶力・判断力、動体視力の衰えは確実ですから、ちゃんと見極めてもらうのが自分の為にもなりますね。
運転免許の自主返納の実態
2017年中の運転免許の自主返納は42万2033件(暫定値)で、前年より7万6720件増えたそうです。
しかも、そのうち75歳以上が約6割:25万2677件。
交通事故を回避するためにも、多くの人が運転免許の自主返納をしていることが分ります。
誰しも、いずれそういう日が来るのは分りますが、もし車を手放さなくならなくなったらどうすればよいのでしょうか?
自動運転の車に乗る
お金のある人は、当然この選択でしょうね。
自動運転のレベルは以下のように決められていて、自動車メーカーの開発競争が激しいです。
これらの自動運転機能が実現されれば、高齢者にとってはとてもありがたいことです。
- レベル1:自動ブレーキ、車間距離の維持、車線の維持
- レベル2:高速道路におけるハンドルの自動操作(自動追い越し、自動合流・分流)
- レベル3:運転操作を全て自動で行い、車両が要請したときのみドライバーが対応
- レベル4:限定地域での無人自動運転サービス、高速道路での完全自動運転
- レベル5:完全自動運転
レベル1は実用化済みで、レベル2の普及も始まっています。
レベル3は東京オリンピックの年:2020年を目途に実用化する予定です。
国交省は、更に高齢者向けの安全運転サポート車(ver.1.0)を「ベーシック」「ベーシック+」「ワイド」の3タイプに分類して、それぞれ以下の機能をつけるそうです。
- ベーシック:低速自動ブレーキ(対車両)、ペダル踏み間違え時加速抑制装置
- ベーシック+:自動ブレーキ(対車両)、ペダル踏み間違え時加速抑制装置
- ワイド:自動ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違え時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライト
歳とってもあっちこっちドライブしたいしなぁ~
いくらぐらいで買えるのかなぁ~
年金生活者にはキツイだろうな~
退職金貯金、無くならないうちに買いたいよ。
地域の公共の交通機関を利用する
一般庶民は、先ずこの辺りが車の代替手段ですよね。
私が住んでいる市では、65歳以上で運転免許証を返納した人は区バスの運賃が半額に設定されています。
これ以外にも地域によっては、福祉バスを利用すると言う方法もあります。
また、地域ボランティアで病院の送り迎えや買い物のヘルプを利用すると言う方法もありますね。
まとめ
記事を書き始めて、これほど高齢化の肌身に感じたことはなかったです。
まだまだ70歳には時間がありますが、あっと言う間だろうし。
こう言うことも将来の計画の中に入れておかなきゃいけないんだなって思っちゃいました。
まだまだ若いって思っていたいし、若さを保つための方法をポジティブに語るってのも大事なんだけど、人生100年なんて言いながら運転免許更新は75歳が限界?なんてことが見えて来て
う~ん、色々準備しておかなきゃなんだね。
ってことで、今日は終わることにする。(^^;)v